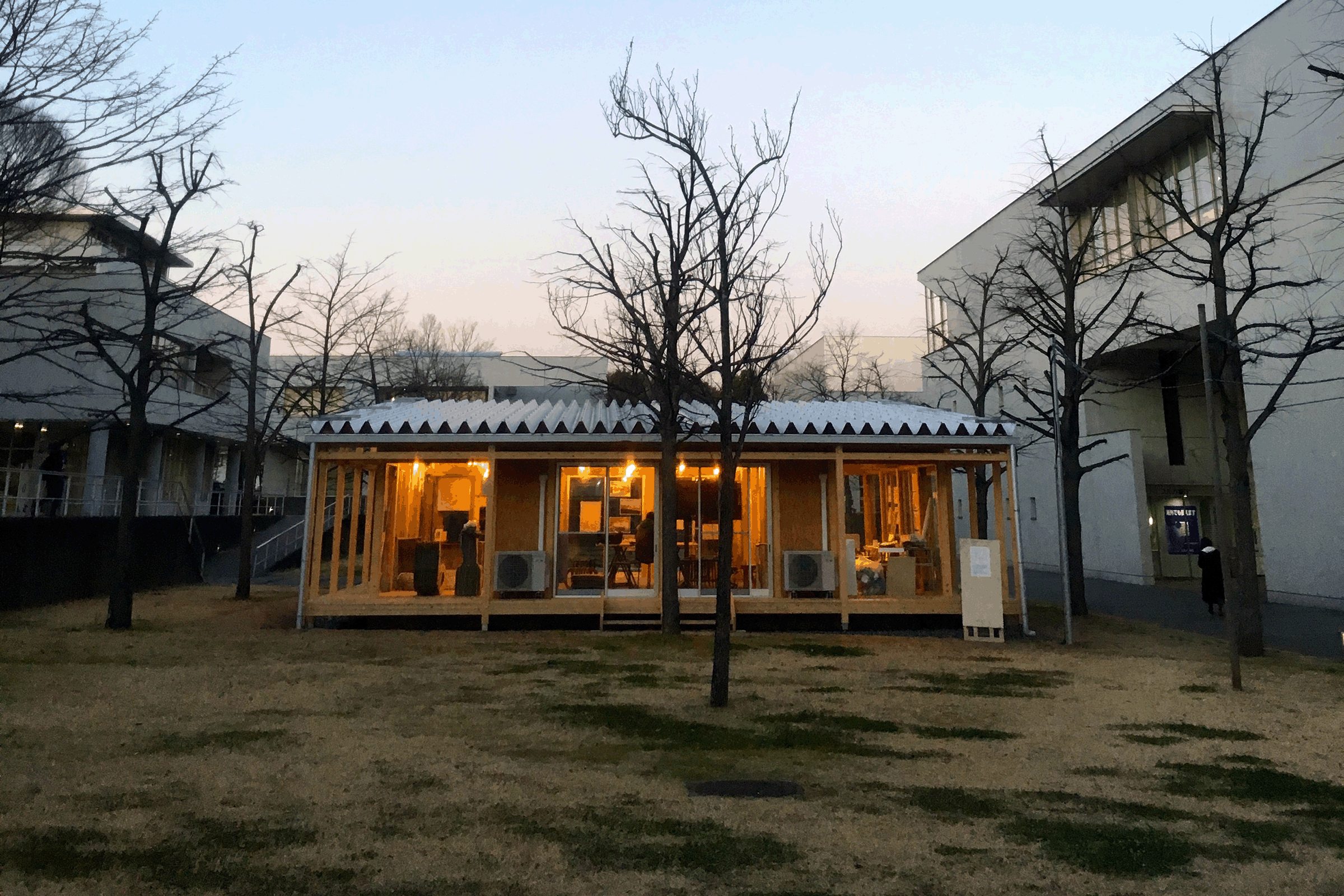枕はいらない。*1 みんな、広間に集まっていた。ノートPC、書類の束、お菓子とペットボトル。夜は更けてゆく。2009年の9月、ぼくは、学生たちとともに家島(兵庫県)に出かけた。Studio-Lの「探られる島」プロジェクトに合流するためだ。そして、このときの出会いや体験は、いろいろなかたちでいまの活動につながっている。5年目の「探られる島」プロジェクトでは、参加者が二人ひと組になって、家島の人びとを訪ねて話を聞き、ポスターをつくることになっていた。
【2009年9月5日(土)|大広間で作業がつづく(いえしま荘)】
家島での逗留先は、「いえしま荘」だった。ポスターづくりは、二人ひと組になって取り組むので、おおかた、ひとつのPCを二人でのぞき込むようなスタイルになる。それぞれのペアは、取材先はちがうものの「ポスターづくり」という同じ作業をすすめる。どのようなことば(コピー)を添えるのか、どのようなデザインにするのか。それぞれのペアのセンスと能力しだいだが、完成させる期限は共通だ。だからこそ、「別々」でありながら「同じ」場所に集まっていることが重要なのだ。適度な距離を保ちながら、わいわいと手を動かす。ばらばらのようで、一体感がある。(それなりに)作業に集中しているが、賑やかな空気が流れる。つまり、大きな部屋にみんなが集うことによってつくられる〈場所〉だ。一番わかりやすいのは、このときのように、畳の大広間に座卓と座布団を並べる「宴会」のセッティングだ。いくつものペアが「つかず離れず」の関係を保ちながら作業に没頭できる。ちょっと気になれば、隣のペアのようすをのぞき込んだり、軽くことばを交わしたりする。お互いの進捗を意識しながら、ゆるやかな競争と協調が息づく。その後も、全国のいろいろなまちに出かけてポスターづくりのワークショップをおこなっているが、似たような作業環境があるとき、ぼくたちの満足度は高い。もちろん、行き先の事情によって、できることはかぎられている。日程や人数なども毎回ちがうので、いつでも似たような状況で「キャンプ」を実施できるかどうかはわからないが、「別々」に「同じ」ことに取り組む環境は、なかなか居心地がいいものだ。
【9月6日(日)の朝|作業をしながら?倒れた参加者たち(ピンぼけ)】
一緒に過ごすことのできる大きな部屋(広間)にくわえて、もうひとつ重要なのは、眠くなったらすぐに布団やベッドにたどり着けるということだろう。大広間で作業を続けて、眠くなったらすぐに横になる。しばらく休んで、また作業に戻ることもできる。あるいは、眠さに耐えられずに「寝落ち」することもある。布団やベッドがすぐそばにあれば、安心して「寝落ち」に備えることができる。言うまでもなく、夜を徹して作業をすれば、質の高い成果が生まれるという保証はない。むしろ、無駄を省いてテキパキと仕事をすすめて、翌日のためのエネルギーを蓄えたほうが、身体にも優しいはずだ。それでも、大広間で更けてゆく夜は、悪くない。ぼくたちの学びは、生活とともにある。日常生活は、いつでも学びに満ちている。大学の「キャンパス」のありようをじぶんたちで構想するということは、つまり、じぶんたちの生活(生活スタイル)をつくってゆくことである。「生活のある大学」は、寝食をともにしながら学び、自由闊達に語らう場所をつくることを目指している。書を読むこと、学ぶことを活動の中心に据えて暮らす。そのスタイルは、とくにあたらしいものではない。たとえば、明治30年に記された『福翁自伝』につぎのような一節がある。少し長くなるが、引用しておこう。
学問勉強ということになっては、当時世の中に緒方塾生の右に出る者はなかろうと思われるその一例を申せば、私が安政三年の三月、熱病を煩うて幸いに全快に及んだが、病中は括枕で、座蒲団か何かを括って枕にしていたが、追々元の体に回復して来たところで、ただの枕をしてみたいと思い、その時に私は中津の倉屋敷に兄と同居していたので、兄の家来が一人あるその家来に、ただの枕をしてみたいから持って来いと言ったが、枕がない、どんなに捜してもないと言うので、不図思い付いた。これまで倉屋敷に一年ばかり居たが、ついぞ枕をしたことがない、というのは、時は何時でも構わぬ、殆ど昼夜の区別はない、日が暮れたからといって寝ようとも思わず、頻りに書を読んでいる。読書に草臥れ眠くなって来れば、机の上に突っ臥して眠るか、あるいは床の間の床側を枕にして眠るか、ついぞ本当に蒲団を敷いて夜具を掛けて枕をして寝るなどということは、ただの一度もしたことがない。その時に初めて自分で気が付いて「なるほど枕はない筈だ、これまで枕をして寝たことがなかったから」と初めて気が付きました。これでも大抵趣がわかりましょう。これは私一人が別段に勉強生でも何でもない、同窓生は大抵みなそんなもので、およそ勉強ということについては、実にこの上に為ようはないというほどに勉強していました。
『新訂 福翁自伝』(「塾生の勉強」岩波新書, 1978, p. 80)
学びと生活が一体化すること。それは、じぶん(たち)の時間を自在に使える贅沢を味わうということだ。それは、あらかじめ(常識的な)「時間割」に集約することのできない、特別な時間だ。前にも書いた が、「滞在棟」を使うためには、お互いの時間を差し出す覚悟が求められる。たとえば「合宿」の場合(ぼくたちの「キャンプ」の試みもそうだが)、一泊二日というように、事前に時間を確保する必要がある。参加表明は、すなわち、じぶんの時間を差し出す決意の証だ。遠くのまちに出かけるときは、「逃げ場」がないので、必然的に学びと生活が一体化する。いつもの環境を離れて集中的に学べるのが、「合宿」のいいところだ。
もう少し考えてみたいのは「不意の宿泊」だ。それは、時間を忘れるほどに勉強に没頭していて、あるいは語らうことに夢中で、(終電/終バスを逃して)家に帰れなくなるような場合の宿泊だ。提出期限に間に合わなくて、やむを得ず「残留」するのとはちがう。あるいは、泊まりで向き合わないと課題が終わらないような切迫した状況でもない。
知的な没入が、ふだんの時間感覚を揺さぶり、160年前の書生のような暮らしへと誘うとき。ときめくような会話をとおして、時計とカレンダーで窮屈になっているじぶんに気づいたとき。そんなときこそ、木立を抜けて「滞在棟」に向かうのだ。
(つづく)
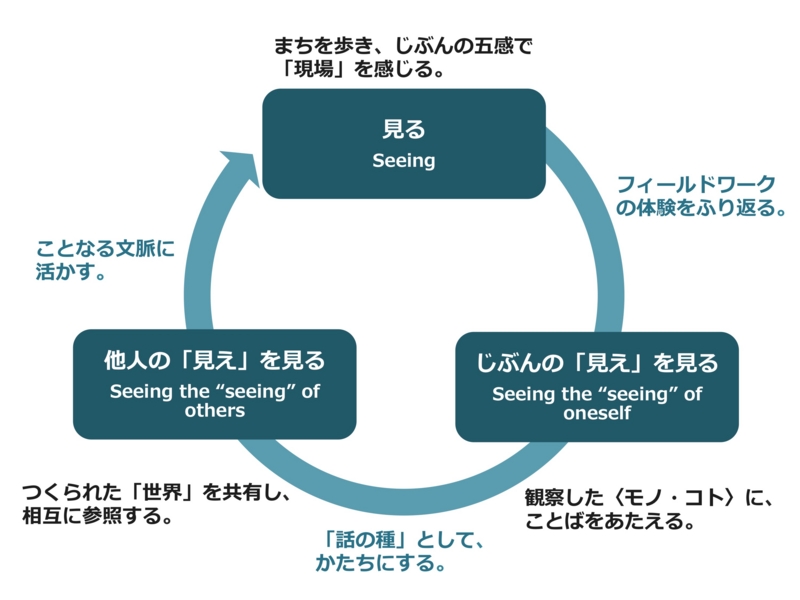
 【2016年3月2日|荒穂神社】
【2016年3月2日|荒穂神社】