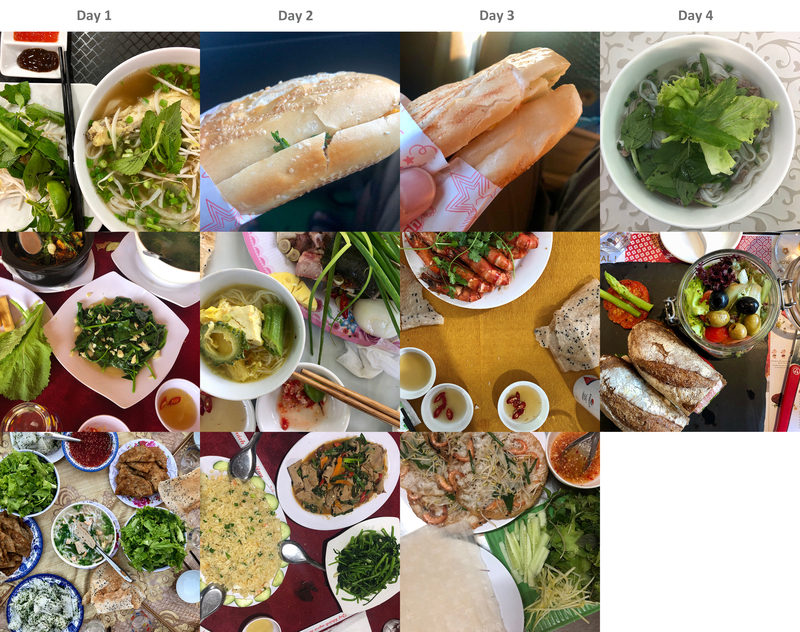「余白」から考える
案内してもらうつもりで待っていると、奥から店員がやって来た。そして、席が空くまでしばらく待つことになると告げられた。店のなかを見渡すと、いくつも空席が見える。満席ではないはずなのに、ぼくは、店の前で待たされることになった。きっと、似たような経験があるはずだ。なぜ、ぼくはすぐ席に案内してもらえなかったのか。空いているのに、埋めることができない、埋めようとしないのはどういう事情によるものなのか。空いているじゃないかと言って、強引に掛け合ってもよかったのかもしれない。
一人の客として向き合っていると、この状況はわかりづらい。レストランという場所は、さまざまな〈モノ・コト〉の連携によってつくられているからだ。たとえば厨房にはシェフがいるし、フロアの担当も、準備や片づけを担うスタッフもいる。絶えず注文の情報が飛び交い、料理をのせた皿が行き来する。客を席に案内する役目には、その移りゆく店内のようすを逐次考えに入れながら、切り盛りすることが求められているのだ。空席があったとしても、店にいる客からの注文で厨房がフル回転しているときには、あらたに客を迎えることは避けたい。しばらく落ち着いてから、準備が整ってからになる。
つまり、空席があるのにぼくが席につけなかったのは、その時、一人の客を受け容れる余裕のない状況だったからだ。それは、すでに食事をしている客たち、当日働いていたスタッフの人数、目に見えない厨房の事情など、さまざまな〈モノ・コト〉のようすから、そう判断されたのだろう。
すぐに席に案内されたとしても、こんどはメニューを眺めたり注文したりするのが遅れたかもしれない。注文できたとしても、すぐに料理が運ばれてくるとはかぎらない。余裕がないとき、「余白」が必要になる。結局のところ、その時のレストランの「キャパ(許容力)」が問題だったのだ。そして、「キャパ」の有無が、店内に入ったときのコミュニケーションに表れたということだ。
どこにでもありそうな、このちいさなエピソードを入り口に、「余白」について考えてみたい。一人でも多くの客にサービスを提供し、レストランの売り上げを増やすという観点で考えれば、できるかぎり空席を減らしたほうがいい。だが、ぼくがしばらく待たされたという(ちょっとした)出来事は、時と場合によっては空席をつくっておくこと、つまり「余白」を残しておくことが、最良な判断になりうることを示唆している。たんに売り上げを伸ばすだけではなく、客の満足度を高めたり、クレームを受け取るリスクを減らしたり、あるいはスタッフへの負荷に配慮したり。さまざまな理由で、しばらくの間は客を待たせて、空席を残しておくという判断になる。
こうした考えをふまえて、自分自身のまわりを眺めてみると、さまざまな形で、「余白」との向き合い方がデザインされていることにあらためて気づく。引き続き、飲食店を例に考えてみよう。冒頭の例とは対照的な、たとえば、いまどきの牛丼屋の「余白」はどうだろう。多くの店はカウンター席だけで、案内されるのを待つ必要はない。空席を見つけて、自分でそこに座るだけだ。店によっては、自動販売機でタッチパネルに触れたとたんに厨房に注文の情報が届く。水やお茶は、セルフサービスだ。店員とことばを交わすこともない。そもそもがファストフードの部類だから、長居する客はあまりいないはずだ。単価は安いかもしれないが、一連のサービスの流れに、ほとんど「余白」は見当たらない。一杯でも多く売るために、「余白」を減らすための工夫が盛り込まれているのだ。このように、とにかく空席を減らそうという方針であるならば、無理がないように回転率を上げればいい。つまりは、効率化である。人件費を節約しつつ、マニュアル化、単純化・自動化などをすすめる。

ジョージ・リッツアは、こうした一連の合理化の仕組みを、象徴的に「マクドナルド化(MacDonaldization)」と呼んだ。*1「マクドナルド化」は、効率性、計算可能性、予測可能性、そして制御という4つの側面を実現させていることで性格づけられる。客のふるまいが、データとして蓄積されていけば、さらに「余白」との向き合い方が繊細に調整されていくことになるだろう。じつは、それを歓迎する客もたくさんいるのだろう。
当然のことながら、「余白」は空間的な側面だけでとらえられるものではない。席に案内されなかったという出来事のなかには、すでに「余白」の時間的側面がふくまれているからだ。空席がないことは、空間的な状況としてすぐさま観察されるが、じつはその状況がもたらされているのは、調理という過程にかかわる時間的な事情によるものだ。その意味で、「余白の理由」は、空間的・時間的な側面から考えいく必要がありそうだ。
ところで、「マクドナルド化」を推奨して、「余白」を減らすことを目指せばよいとはかぎらない。合理化をすすめて「余白」のない場所ができること自体にも価値はあるはずだが、いささか慌ただしい。素っ気ない感じもする。友だちとおしゃべりを楽しみながら、外の景色に目をやりながら、ゆっくりと食事をする時間も大切だ。そんなときには、急かされることなく、席についてからメニューを眺め、料理がはこばれてくるまでの時間さえも愉しみたい。そのためには、ぼくたちにも余裕がなければならない。そう考えると、「余白」には心理的な側面もあることに気づく。心に余裕がないと、人との接し方にも影響がおよぶ。不要なミスを招くこともある。
ぼくたちの日常生活のなかには、どのような「余白」があるのか。その意味や価値に、どうすれば気づくことができるのか。そして、たとえば一日の時間の流れにどのように「余白」を配置すればよいのか。まずは、身の回りにある「余白」をさがすことからはじめよう。(つづく)
*1:ジョージ・リッツア(1999)『マクドナルド化する社会』早稲田大学出版部