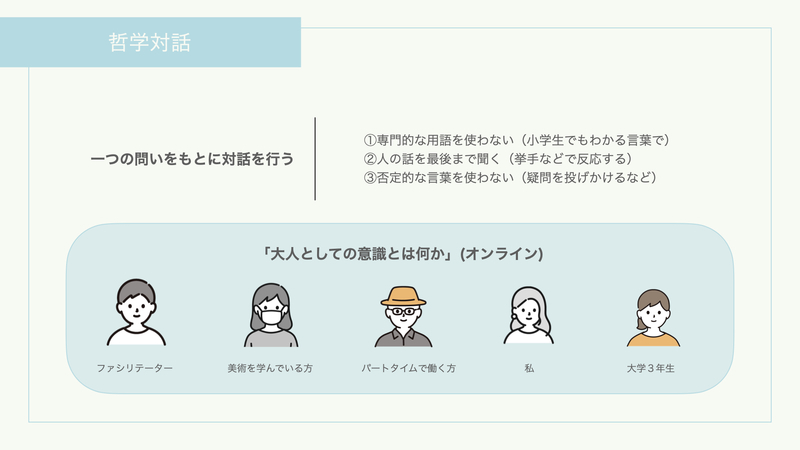(2022年8月7日)この文章は、2022年度春学期の成果報告として提出されたものです。体裁を整える目的で一部修正しましたが、本文は提出されたまま掲載しています。
中田 江玲
なぜこの研究を行うのか
① 社会的背景
2022年、著名な映画監督による性加害が立て続けに告発されたことが契機となり、日本の映画業界におけるハラスメント行為の常態化に対する批判が強まった。同年3月18日には映画監督6名によって構成される映画監督有志の会が「私たちは映画監督の立場を利用したあらゆる暴力に反対します」という声明を出すなど [1]、映画業界における労働環境改善に向けた活動が従来よりも顕著に見られるようになった。
映画製作を進める上での決定権を多く持つ監督という立場は、その特性により映画製作の現場において優位的である。映画撮影の現場は、慢性的な人材不足・長時間の拘束・低賃金などの不安定で劣悪な労働環境であるため[2]、身体的・精神的負荷がかかりやすい。このような負荷は権力に関係なく生じるが、監督やプロデューサー、助監督などはそれらの立場が持つ優位性を利用してハラスメントというような暴力行為に至りやすい。
また、映画撮影の現場において契約書を交わすことなく就労しているスタッフが多いため、個人が権利を主張しにくい環境であり、それによって権力関係をより強固なものにしている。2019年度に経済産業省が行った調査によると、映画スタッフのうち約8割がフリーランスであり、そのうち仕事に従事する際に契約書を貰っていないと答えた人が過半数を占める[2]。働く内容に合意が取れていないまま撮影現場に入ることで柔軟に働かざるを得なくなり、過度な要求に対しても異議を唱えにくくなっている。
映画が芸術的な文脈において語られることも、監督という立場の権力を強めている要因の一つであると考えられる。ビジネスとして商業映画を製作する場合、その映画には資金に相応した、あるいはそれ以上の価値が求められる。映画の価値は娯楽性と芸術性という2つの面によって評価されるものであり、前者は興行収入によって、後者は個人によって判断される。映画祭において受賞する映画が審査員による話し合いで決められることは、映画の芸術的価値が個人に委ねられていることが分かる例である。製作中、つまり公開前の映画である場合、興行収入によって映画の娯楽的価値を量的に判断することは難しい。そのため撮影したカットに価値があるか否かの判断は監督個人の芸術的感覚に委ねられる場合が多く、監督の曖昧な指示が許容されやすくなっている。監督による指示の正当性を求めない状態は、撮影を進める上でスタッフや役者との合意形成を無視できる権力を監督という立場に与えることになる。
映画監督という立場を利用した加害行為が無視されてきた背景があるからこそ、私は『暴力性』という言葉を用いながら向き合うことの重要性を感じている。そして、映画監督という立場が『暴力性』を必ず備えてしまうからこそ、それに警戒し、思考と実践による終わらない抵抗を持続させなくてはならない。
② 個人的背景
私はカメラを持って撮影し、監督として演出を行い、編集をする。自ら映画監督であると名乗れるほどの実績はないが、監督として携わった映画を見てもらえる機会がここ数年で少しずつ増えている。そのような状況の中、今まで自分が監督として携わった映画製作を振り返り、自分が備える暴力性に対して自覚的であったか不安に思うことがよくある。自分の属性に対する理解が深くなければ、自らが有する特権に気付かず、無自覚な差別を行ってしまう。映画監督という立場を経験し始めたばかりの私には、その立場が備える優位性や権力によって生じる暴力を想定しきれておらず、無自覚に誰かを抑圧しているのではないだろうか。
フィクション映画を作る際、監督やプロデューサーが企画の立案を行い、脚本家が脚本を執筆する。近年は映画監督が脚本も兼任することが多いため、脚本の中に登場するキャラクターが監督の想定を超える動きをすることはほとんどないと言えるだろう。一方で、映画撮影現場になるとキャラクターの主体が役者まで拡張されるため、監督が想定していたものとは異なる動きをキャラクターが行う可能性がある。私には、役者がもたらすキャラクターの未知性に対して驚き、十分な合意が得られないままに監督という立場を利用して指示通りに演じさせようと試みてしまった経験がある。
映画撮影の現場では、監督が行う演出に対して役者は「はい、分かりました」と応答し、議論することなく演技がなされる場合が多い。私が監督として参加した映画の現場でも役者と意見がすれ違うことは特になく、キャラクターの主体が映画撮影の現場で拡張されるという作用を意識していなかった。役者によって与えられるキャラクターの未知性を私が初めて自覚したのは、前回の映画撮影時に役者から「私のキャラクターはそう振る舞わないと思います」と意見を言われたときだった。今でもその時に私がつけた演出が間違っていたとは思わないが、その時の対応に対してはもっと別の方法があったと考えている。物語全体を考えながら、各シーンにおけるキャラクターの動きに整合性があるかを確認するのは監督という立場が担う役割である。そのため監督は役者と話し合いながら、キャラクターの主体を共に作り上げていく必要がある。一方で、キャラクターの主体が役者まで拡張したことを無視し、役者がもたらす未知性を恐れ、十分に議論もしないまま排除しようとすることは暴力的な行為である。
映画撮影時に監督が役者に演出を行う際は、役者という立場のもつ中動性に意識を向けなければならない。役者が自らの身体を能動的に動かして演技をしていたとしても、そこには監督の意向に基づき動かなければならないという受動性が権力関係によってもたらされていることも無視できない。監督の演出通りに役者が演技を行ったとしても、監督が(無自覚であっても)その立場を利用して役者の自由意志を奪っている可能性は常に存在している。このような役者という立場のもつ中動性を理解した上で、なるべく監督と役者が合意した演出の上で演技が行われるように、キャラクターの行動原理や行動の意図、または感情の表出方法について話し合うべきである。とはいえ、権力関係の中での合意は双方の意思を完全に反映しているとは言い切れない。そのため監督という優位な立場からは、役者の自由意志を奪わないための働きかけを行うことしかできない。
私はこのような背景から、映画監督という立場が備える暴力性を自覚しながらも、それに抵抗し続けるための研究を行うことに決めた。
研究の目的
まず、映画監督という立場の持つ暴力性をなくすことは不可能であるということを念頭に置く必要がある。映画監督という立場が持つ優位性はその決定権に由来しているが、映画製作を進めるための判断を行うことは監督という立場のもつ役割であるためそれを回避することは不可能である。本研究は、課題解決といったような正解を求める活動ではない。
この研究の目的は、映画監督の持つ暴力性をなくす特効薬を見つけることではなく、映画監督という立場が備える暴力性についての理解を深めることである。
また、本研究では映画監督という立場にのみ焦点を当てているが、映画製作において暴力性を備えているのは監督だけではないということも明記しておきたい。映画監督という立場から振るわれる暴力の可能性にのみ気をつけ、警戒すればよいわけではない。私が最終的に目指すのは、映画製作に関わる全ての人が安全に、安心して製作活動に携わることができる環境である。
研究方法
フィクション映画監督という立場が持つ暴力性に対する理解を深めるためには、映画製作の現場に入り、フィールドワークを行うことは必要不可欠である。一方で、どのような立場から観察を行うかについては選択の余地がある。1つ目の方法として、調査者として映画製作に直接関わらずに記録のみを行うことが挙げられる。2つ目は、映画監督以外の立場から映画製作に関わり、調査を行う方法だ。そして3つ目の選択肢は、研究者自身が映画監督として映画製作を行う調査方法である。私はこの中から、3つ目に挙げた方法を実践することに決めた。
この研究テーマを決定してから、監督以外の役職で撮影の現場に入った。調査目的ではなかったが、その経験から監督自身でなければその立場が備える暴力性について気付けないであろうと感じた。調査者として映画監督という立場の備える暴力性を観察するためには、暴力が実際に実践されなければならない。そのようなことはあるべきではなく、なおかつその場合は研究目的である「フィクション映画監督という立場が持つ暴力性への抵抗」から外れてしまう。一方で、研究者自身が映画監督として映画製作に関われば、暴力の実践可能性を感じた時点でその立場のもつ暴力性を観察し、記録することができる。実際に今までの私が監督として映画製作を行う際、「このように振る舞うと、監督の持つ権力によって相手を威圧してしまう可能性がある」と感じ、気をつけた経験がある。卒業をした後も私自身がフィクション映画を監督する際にこの研究の内容を実践していくためにも、研究者自身が映画監督として映画製作を行う調査方法が最も有用であると考えた。
本研究では、研究者である私自身が監督としてフィクション映画のある特定のシーンの製作を複数回行い、その過程を記録する。製作する映画への理解度によって権力関係が強まることを懸念するため、映画の製作は全て同じ役者とスタッフで行う。また、この研究で観察する映画製作は<本読み>から<上映>までとする。
「なぜこの研究を行うのか」で挙げたように、映画監督はその立場を利用して、役者との合意形成を回避しながら演出をすることが可能である。一方で、これは役者の自由意志を奪うことにつながるため、行われるべきではない。このような暴力が生じやすい構造を考慮し、本研究では映画製作の際にLearning Trough Discussion(=LTD)という手法を用いる。これはアイダホ大学のWilliam F. Hill 博士が1962年に考案した共同学習法の技法であり、論理的・批判的思考スキルの改善や、言語スキル・コミュニケーションスキルの改善などの効果が得られるとされている。[3]映画製作において表現の擦り合わせを行うためには、脚本を正確に読み取り、キャラクターなどの行動についての考察を言語化する能力が必須である。もしこのような能力がなければ、演出を行う際に合意形成を試みることができず、監督という立場を利用して、暴力的になる可能性が大きくなる。LTDを使用することにより、演出意図の説明が要求されやすくなる環境を作り、映画監督という立場が持つ暴力性への抵抗を示していく。
本研究では、映画製作における脚本読解用にLTDの内容を以下の通りに応用する。

卒プロ2に向けて
2022年度春学期は、映画監督という立場や映画業界のもつ構造的な問題点について明らかにしてきた。卒プロ2では、映画監督という立場が備える暴力性に対して警戒しながら、監督として実際にフィクション映画を制作していく。
参考文献
- action4cinema /日本版CNC設立を求める会│「私たちは映画監督の立場を利用したあらゆる暴力に反対します。」(2022/3/18) https://action4cinema.theletter.jp/posts/877aa260-a60c-11ec-a1bd-3d3b3c9fc3bd
- 経済産業省│「映画制作の未来のための検討会 報告書」(2020/3) https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000489.pdf
- 安永悟│「実践・LTD話し合い学習」ナカニシヤ出版(2016)