美波で考える・つくる
更新記録
(2024-3-18)美波キャンプ(徳島県)の準備を本格的に開始、下見・打ち合わせで美波町へ
フィールドワーク型のワークショップを「キャンプ」と呼んで、学生たちとともに全国のまちを巡っています。まちで出会った人びとに話を聞いて、ひと晩でポスターをつくります。やや荒削りではあるものの、まちに暮らす人びとの姿をできるかぎり自然に映しとり、ことばを添えます。「まちに還す」ことの大切さと面白さを味わいながら、ポスターづくりのプロジェクトは15年近く続いています。
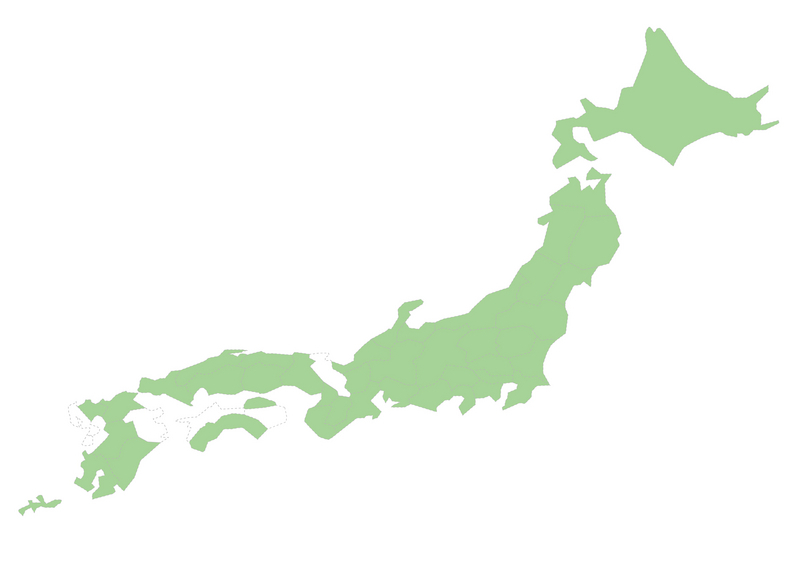
◎キャンプ(2004〜)2024年3月20日現在 → 地域別インデックス
https://camp.yaboten.net/entry/area_index
【きっかけ|つながりの系譜】
(準備中)
美波キャンプ
- 日時:2024年5月24日(金)〜26日(日)(現地集合・現地解散)*24日は移動日
- 場所: 美波町(徳島県)
- 参加メンバー:加藤文俊研究室 XX名(学部生 XX名・大学院生 X名・教員 1名)*参加者確認中
スケジュール(暫定版)
5月24日(金)
- 16:30ごろ 集合:谷屋(たんにゃ)(〒779-2304 徳島県海部郡美波町日和佐浦184)(予定)
- 17:00 オリエンテーション(仮)
5月25日(土)
- 10:00 オリエンテーション
- 10:30ごろ〜14:30ごろ インタビュー/フィールドワーク(グループごとに行動・取材先に応じて随時スタート)
- 15:00ごろ〜 デザイン作業(グループごとに行動):インタビュー/フィールドワークで集めてきた素材をもとに、編集作業をすすめます。
- 18:30 夕食(食後も引き続きデザイン作業)
5月26日(日)
- 00:00 ポスターデータ提出(時間厳守)
- 10:30ごろ〜 ポスター展準備 会場:谷屋(たんにゃ)(〒779-2304 徳島県海部郡美波町日和佐浦184)(予定)
- 12:30ごろ〜 「美波の人びとのポスター展」
- 成果報告会 12:30ごろ〜(ふり返りビデオ上映 13:00ごろ〜)
- 14:30ごろ〜 解散



2024年3月18日|打ち合わせと下見




















