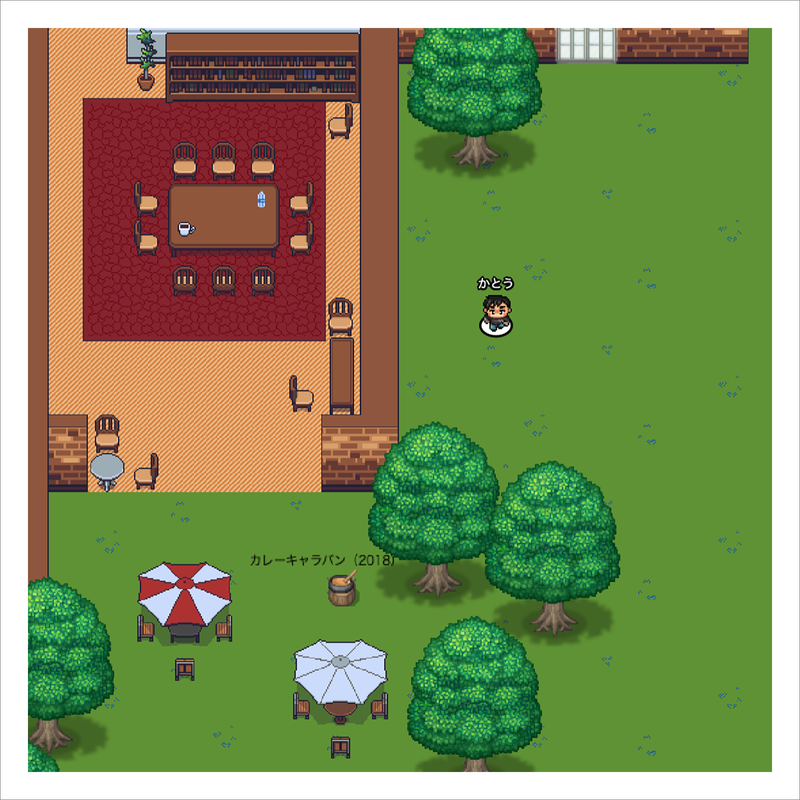この文章について。*1
採集される日常
オランダの写真家、Hans Ejikelboomによる『People of the Twenty-First Century』には、彼が街頭で撮り続けてきた写真が並ぶ。彼は、一日に20分から数時間をかけて80枚ほどの写真を撮り、それを毎日、20年間続けてきたという。それぞれのページは、たとえば「赤いジャケット」「ベビーカー」「ルイヴィトンのバッグ」のように、テーマごとに構成されている。その日の「お題」を決めて、対象となった装いや持ち物などを塊集するというやり方だ。オランダの各都市をはじめ、上海、ニューヨーク、東京など、いくつもの都市で撮影されたスナップ写真なのだが、一つひとつの都市の歴史や文化の多様性を忘れて、被写体となった数多くの人びとのなかに、まさに(タイトルが示唆する)“21世紀の人びと”の共通性・同質性を見出すことができる。
いっぽう、Jason Polanの『Every Person in New York』は、2008年の3月に最初の投稿があってから、いまなお続いているブログである。タイトルのとおり、ニューヨークの“すべての人”をスケッチしようという試みで、説明文によると、彼は決められた場所に定期的に立って、2分間でスケッチを描くらしい。道行く人にわざわざ足を留めさせることなく、2分というわずかな時間であるからこそ、日課のようにスケッチを描き続けることができるのだろう。2015年には、ウェブに掲載されていたスケッチが束ねられ、ブログと同名の書籍が刊行されている。収録された30000点におよぶスケッチを眺めていると、いずれ本当に“すべての人”が描かれるような気にさえなる。むろん、書籍が刊行されてからもスケッチは続けられている。興味ぶかいのは、彼がいつ頃どこでスケッチを描くかという情報が提供されているという点だ。もし自分もスケッチに描かれたい場合には、その時間・その場所に赴くというわけだ。対象にえらばれれば、一連のスケッチのなかに自分の姿が織り込まれることになる。*2
もちろん、他にも類似の試みはたくさんある。私たちは、このような夥しい数の写真やスケッチのコレクションに触れるたびに驚嘆し、しばし時間を忘れてページを繰る。私たちが、日常を採集する試みに惹かれるのはなぜだろうか。
個性に近づく
私たちは、フィールドワークに出かけると、調査者としての役割を意識するようになる。そして、ごく自然に、普遍抽象的な言明を求める。具体的な事例をとおして、一般化を試みる。もちろん、調査と呼ぶからには、汎用性のある成果に結びつくことは大切な使命だ。だが、「考現学」的なフィールドワークの強みは、「個性」を扱うアプローチだという点にある。徹底して、人びとの暮らしやまち並みの詳細な観察と記述を試みる。個別具体的な目線に自覚的になると、知識のあり方だけではなく、コミュニケーションのスタイルまでもが変わってくるはずだ。それは、「例示的定義」をあたえていくことに他ならない。
例示的、個別具体的であるからこそ、私たちは実態をともなうかたちで共感したり反発したりすることができるのだ。だから、一般化・概念化への欲求をひとまず捨てる覚悟が必要だ。自分自身や身近な知人、友人、そして自分の身の回りの出来事と比べながら、一枚一枚の写真やスケッチを注視する。そのとき、私たちはたんにその時間を愉しんでいるだけではなく、人びとの暮らしやまち並みについて、自分なりの理解を創造しているのだ。これは、専門家が撮ったり描いたりした「決定的瞬間」ではない。何枚もの写真やスケッチを並べ替えたり分類したりしながら、少しずつ私たちの日常生活の輪郭が描かれてゆく。冒頭で紹介したような事例をふくめ、私たちが「考現学」的な方法や態度に惹かれるのは、おそらく量が質に変換されうることを実感するからだ。
こうした「考現学」的な調査には、多大な時間とエネルギーが必要になる。冒頭で紹介したように、自分なりのやり方を考案し、日常的に続けられる工夫と、なによりも、尽きることのない情熱があれば、一人で実践できるのかもしれない。もちろん、誰かの力を借りながら調査をすすめるやり方もある。今和次郎の『モデルノロヂオ』(1986, 復刻版)を見ると、彼自身によるまち歩きの報告とともに、連名で書かれた記録も数多くある。なかには、「採集者」として数名の名前(今に師事していた学生かもしれない)が並び、今和次郎自身は「説述」という役割を担って書かれたレポートもある。あるいは、『モデルノロヂオ』の共編著者である吉田謙吉(今和次郎の後輩にあたる)を「参謀総長」と呼んだり、「〜君に現役に廻ってもらって」といった記述があったり、まちを踏査するための調査隊ともいうべきチームが編成されていたことがうかがえる。
複数のメンバーから成るチームを編成して「考現学」的な調査をすすめようとする際、どのように調査を設計すればよいのだろうか。チームワークや成果のまとめ方など、考えるべきことは多岐にわたる。なかでも、まず重要だと思われるのは、「調査マニュアル」ともいうべきものを整備することだ。いわゆる「ローラー作戦」のように広い範囲をカバーする場合、あるいは何度かに分けて同じフィールドを訪れて時間的な変化をとらえたい場合には、対象となるフィールドをいくつかに区分したり、時間のシフトを決めたりして、分担することになる。数を数えるという単純な作業であったとしても、調査対象を的確にとらえるためには、調査者のあいだに生じうるバイアスを極力減らす努力が必要で、そのためには、情報の共有やトレーニングが欠かせない。
今和次郎らによる調査報告に触れるとき、私たちはイラストや図解などに目が行きがちだが、多くの場合、調査の過程にかんする記述や「調査規定」が付記されている点にも注目したい。成果のみならず、方法そのものも記録・公開することは、調査の設計という観点から、きわめて示唆に富んでいる。すでに10年以上前のことになるが、ゼミの学生たちとともに、1926年に行われた「銀座風俗採集」を辿るフィールドワークを実施したことがある。もちろん、すべての面において完全に調査を再現できたわけではないが、実際にまち歩きをはじめるにあたって、オリジナルの記述を全員で確認した。あれこれと想像しながら、私たちなりにアレンジが加えたものの、たとえば、「京橋から新橋までの間を調査区間とす。」「主として西側を調査す。」「調査区間を20分の歩度で歩く事とし、その途上に於て前方より歩み来る人のみを調査の対象とし、立停る人、追い越す人その他一切を調査に加えず。」のように、歩く経路やスピードなど、調査者のふるまいを規定する指針が明記されていたおかげで、不完全ながらも、当時の「風俗採集」のようすを追体験することができた。
フィールドワーカーの想像力
チームによるフィールドワークは、容易ではない。一人ひとりの能力やセンスが問われることもたしかだが、チームですすめるという方針を採用した時点で、私たちはチームづくりの課題に向き合うことになるからである。それは、フィールドワークの基本的なマナーや礼儀をはじめ、記録の方法、情報共有、成果のまとめ、表現のスタイルにいたるまで、「全体」としてフィールドワークを設計する視野が求められる。もう一歩すすんで言えば、調査チームのメンバーが、お互いに(健康的に)競いながら感性や能力を高め合う、「学習コミュニティ」の醸成を目指すことが望ましい。
調査者は、ひとたびチームのメンバーになると、共通のボキャブラリー(調査に関わる専門用語、略称や符号など記述に必要な決まり事をふくむ)を身につけ、つねに適切な方法で情報共有を心がけるよう求められる。チームのリーダーは、「調査規定」の形式化や、メンバーのトレーニング(実習)も計画しなければならないだろう。
ここで重要なのは、調査のためのチームづくりには、重要な問題が埋め込まれているという点だ。というのも、「調査規定」の整備やトレーニングなど、調査方法の形式化は、メンバーそれぞれの個性を奪うことになるからである。チームにおいて「一人前」になることは、「余計なことは考えずに、調査規定のとおりに観察・記録をおこなう」能力を身につけることだ。極端に言えば、いつ、どのような状況でもチームの一員として適切にふるまうことができる、お互いに交代や補完が可能なメンバーになることが要請されるのである。誰がやっても、同じようなデータが収集できること、つまり調査の再現可能性が担保されてこそ、調査の規模を拡大したり、長期にわたってデータ収集を継続したりすることができる。
だが、私たちは、フィールドワークをすすめているとき、しばしば予期せぬ出来事に遭遇する。偶然の出会いや、発想の連鎖が、あたらしい知識の創造に結びつくことを、私たちは経験的に知っている。いっぽうでは「調査規定」を従順に参照し、できるかぎり効率的に調査をすすめていながらも、あたらしい発見のためには五感を開放しておかなければならない。まさにフィールドワークの現場で、(ある程度)臨機応変に判断しながら、調査のすすめかたを修正してゆく態度も必要だと言えるだろう。
私たちのコミュニケーションは、〈見る=見られる〉という関係によって成り立っている。人びとの装いや流行(ファッション)は、まさに視線のやりとりをとおして構成・再構成されるコミュニケーションだと言えるだろう。かつては、モードの先端を牽引する「モデル」たちと出会うために、まちに出かけた。「モデル」たちにとって、街頭は舞台であり、人びとの視線を集めることによって自らの装いへの意識を高め、さらに感性が研かれていった。私たちは、メディアを介して見聞きする流行や風俗を、自分の目で直接たしかめるために路上に向かう。
雑誌などの媒体は、もちろん重要な情報源であり続けるはずだが、ネットワーク環境の変化にともなって、私たちが消費する視覚情報が急速に肥大化している。人びとの装いがスナップ写真として雑誌のページ、さらにはウェブページに定着されるようになり、その過程で、私たちのふるまいや心理構造も少しずつ変容してきたと考えられる。多様な人びとのふるまいは、分類・配列できる対象として理解され、「〜系」「〜クラスター」といった呼称をあたえられて整理される。
分類枠組そのものが、これまで以上に身近な存在になったということだ。私たちは、さまざまな変化に迅速に対応するために、あらかじめ決められた分類枠組や解釈のしかたを、さほど疑うこともなく受け容れてはいないだろうか。すでに述べたとおり、私たちの想像力は、一般化・形式化への欲求を断ち切って、個性に着目することによって刺激される。「モデル」は、そのままコピーするための「ひな形」ではなく、批判の対象であり、また乗り越えるべき対象のはずだ。
「定点観測」のこれから
アクロス(パルコ)が、渋谷・原宿・新宿の3地点ですすめてきた「定点観測」は、1980年にはじまったので、2016年は36年目になる*3。時代は変わり、記録や記述の方法も変化しているが、文字どおり「定点」を決めて調査が続けられてきたことはとても意義ぶかい。これまでに蓄積されてきたデータをどのように活かし、人びとの装いや風俗を読み解くのか。「調査規定」の整備をはじめとする調査の組織化について、いくつかの観点からあらためて考えておく必要があるだろう。
まず、重要だと思われるのは、データを「〜系」「〜クラスター」といった呼称をあたえること自体の意味を問う姿勢だ。私たちはSNSなどを駆使しながら日常生活を組み立てている。視覚情報が肥大化しているとはいえ、デジタルメディアによって、私たちのまちへの関心が駆逐されるわけではない。路上とメディア環境は協調的に併存しているという点をふまえて、あたらしい感性と技術によってフィールドワークの方法を再定義・再編成していくことになるだろう。
そして、被写体となった人物とともに写り込んだ風景に注目することも大切だ。言うまでもなく、全世界的な「トレンド」として語られるファッションや風俗もある。だが、たとえば「定点観測」が、ある地点によって行われたという事実を、あらためて考える必要がある。私たちは矩形に切り取られたスナップ写真を眺めながら、フレームの「外」へと想像力をはばたかせながらも、ローカルな意味づけを試みる。そのいとなみこそが、「考現学」が個性を探究する方法であることを再確認する契機になる。
こうした変化をふまえて考えると、私たちは、人びとの装いやふるまいを「属性」としてではなく、「状況」としてとらえることの重要性に気づくだろう。「〜系」「〜クラスター」という呼称をつかう場合でも、それが固定された「ラベル」であるかのように理解するのではなく、ある条件のもとで場合によっては一時的に生起する「状況」として理解することが重要だ。
近年、ネットワーク環境を前提として、私たちの「モビリティ(移動性)」に関わる諸側面の再編がすすんでいる。ケータイからスマートフォンになり、誰もが高画質のデジタルカメラを持ち歩くようになった。スナップ写真は、ハッシュタグとともに即座にアップロードされ、SNSを介して拡散する。位置情報などは、自動的に写真に埋め込まれるようになった。当然のことながら、私たちのコミュニケーションや人間関係が、組み替えられている。
さらに言えば、いまや自撮りの時代である。ファッションや持ち物の自撮り写真をInstagramなどを介して公開している人は少なくない。これまで時間とエネルギーを投じて整備されてきた「定点観測」の方法が、モバイルメディアの受容・普及にともなって、変化しつつあると考えることもできるだろう。自らをプロデュースし、ネット上に絶え間なくスナップ写真が投稿されている状況は、これまでの「定点観測」の方法にどのような影響をあたえるのだろうか。まさに、私たちが「つねに動いているということ(always on the move)」を明示的に扱う、調査・研究の方法と態度が求められていると言えるだろう。
参考
- Jason Polan(2015)Every person in New York. Chronicle Books. (http://everypersoninnewyork.blogspot.jp/)
- Hans Eijkelboom(2014)People of the twenty-first century. Phaidon Press.
- 今和次郎・吉田謙吉(編著)(1986)『モデルノロヂオ(考現学)』(復刻版)学陽書房