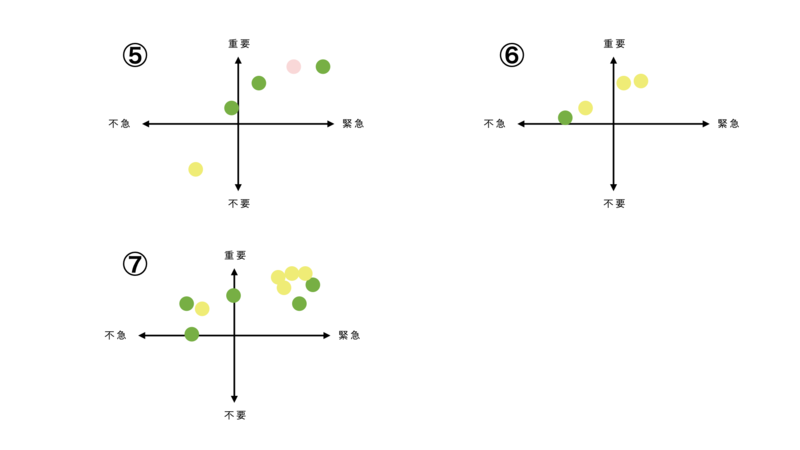(2021年8月7日)この文章は、2021年度春学期「卒プロ1」の成果報告として提出されたものです。体裁を整える目的で一部修正しましたが、本文は提出されたまま掲載しています。
安藤 あかね
私が現在取り組んでいるプロジェクトのテーマを一言で表すと、「主に声だけでコミュニケーションをとるような環境において、どう人を理解して好きになっていくか」です。
これだけではあまり明瞭でないため、このテーマに行き着くまでの経緯を順に説明したいと思います。
当プロジェクトにおいて、非常に重要な存在となっているのが「Vさん」です。
「V」はインターネット上でのハンドルネームのイニシャルで、私はVさんの素顔も本名も知りません。私も同様に、本名ではなくハンドルネームでVさんとやり取りをしています。
Vさんとはどのような人なのか、なぜVさんと関わりを持つことになったのか。そして、関わる中でどのようにしてテーマが決まっていったのかをお話します。
Vさんを最初に知ったのは、今年の1月頃のことです。
私は任天堂が発売しているゲーム「Splatoon2」がとても好きで、上達のために上手いプレイヤーの動画をよく検索して視聴しています。その過程で、Vさんの動画と出会いました。
丁寧に編集されており、説明もとても分かりやすいにもかかわらず、その動画はあまり流行っていないようでした。
投稿した時期の問題(当時は「Splatoon2」の発売から数年経過しており、アクティブユーザーの多い全盛期とは言えませんでした)もあるかもしれませんが、それでも「この人はこんなに充実した内容の動画を作っているのに、何故あまり伸びないんだろう」と感じました。
当時の私は、「インターネット上のコンテンツ共有サイトにおける、投稿者や受容者間でのコミュニケーション(例:コメント欄で起こる会話)の個性」について興味を持っていました。その調査をするにあたり、自分も投稿者の立場に立つ必要があると考え、昨年の8月から不定期で動画共有サイトで動画の投稿をするようになりました。
しかし当然ながら、有名な投稿者が沢山いるこの時代、コメントをもらえる程に投稿が注目されることはなかなかありません。
そんな自分とVさんを、無意識のうちに重ね合わせて見ていたのかもしれません。気付けば毎日Vさんの動画を遡って観始めていました。
きっかけこそ少しの「共感」ですが、一通り動画を視聴し終わった頃にはどういうわけか、Vさんが持つ説明できない魅力を感じていて、動画では飽き足らず配信も観るようになりました。コンテンツ自体というよりも、Vさん自身の話し方や話す内容に注目していました。
Vさんが配信内で話す情報から、彼が男性であり社会人2年目(8月現在)であること、関西在住であること、大学院生時代にTAを務めた経験があることなどを知り、私の中でのVさんのイメージが少しずつ形成されていきました。
いつしか「Vさんと実際に話してみたい。Vさんがどういう人かを知って、仲良くなりたい」という気持ちが強くなった私は、彼があるサイトを経由して行っていた「Splatoon2」のオンラインコーチングのサービスを受けることを決めました。それが3月頃のことです。
サービスは有償で、基本的に1〜2時間を1回とし、およそ2週間の間隔を空け受講します。3回分で合計10000円、私にとっては決して格安とは言えない金額です。
それでも、勿論ゲームの上達という目的もありますが、それ以上にVさんと仲良くなりたい気持ちが大きかったので、迷わず受講を決めました。
初回のコーチングは、3月12日の20時に行われました。
配信でよく聴いていたVさんの落ち着いた声が実際に聞こえてきた時、「本当にVさんが存在していて、まさに今話しているんだ」と心の中で嬉しく思いました。
ですが初回は流石にいくらか緊張していたため、最低限の質疑応答以外、あまり自分から何かを話すといったことはできませんでした。
雰囲気こそ柔らかいものでしたが、お互いにしっかりと敬語を使っており、およそ2時間、決められたコーチングの内容だけを遂行してその日は終了しました。2回目も同様に、滞りなく終わりました。
コーチングの様子に初めて変化が訪れたのは、3回目の受講時のことです。
2時間のコーチングを終えた後に、Vさんとひたすら雑談をだらだらと続けるようになりました。長い時は3時間にも及び、最早コーチングの内容よりも長い時間を雑談にかけています。雑談の主な内容は、好きなゲームといったゲームに関連した話から、承認欲求の話、就活の話など個人的なものまでありました。
ちなみに、後から振り返って気がついたことなのですが、Vさんの「これでコーチングを終わりたいと思いますが、何か質問はありますか?」という発言が、いつも雑談の始まりの合図でした。
5回目の受講の頃には、私も緊張がほぐれたのか、時々Vさんに対してため口が出てしまうようになりました。初めはため口をこぼす度に謝っていましたが、6回目ではあまり謝らなく(気にしなく)なっていました。またVさん側のため口も、ごく僅かですが見られるようになりした。
8回目はVさんがコーチングの後に用事があったため雑談の時間はあまりとれませんでしたが、本来雑談はしなくていいことなのにもかかわらず、Vさんから長く話せないことを最初に提言されました。いつの間にか、私とVさんの間でコーチングの後に雑談をすることが前提となっていたのです。
このような各回の変化を経て、Vさん自身がどう感じているのかは定かではありませんが、少なくとも私は確実にVさんと打ち解けていっているように感じました。
穏やかで真面目だけれど意外とよく笑う、考え方はあっさりしている…などといったVさんの性格が、鮮明に私の中にイメージとして刻まれていきました。
改めて考えると、大学生になってからというもの、この「人と知り合い、何度も会って話し、時間をかけて相手と仲良くなる」経験がめっきりなくなってしまったように思います。
一学期で完結する授業のグループワークなど、その場では上手くやっていたとしても、あくまで作業を穏便に進めるためであり、本当に仲良くしている実感はない、そんな便利だけれどちょっと寂しい刹那的な関係が増えてしまいました。
さらに現在は、新型コロナウイルスが猛威をふるっている影響で、何も考えずに人と気軽に会って話すことが難しくなっています。
そういう意味で、私が現在体験しているこのVさんとのやりとりは貴重なのかもしれない、今はオンラインだからこそできる体験なのではないか、と考えました。
だからこそ、この体験を通して、素顔も本名もわからない、けれどもその人のことを沢山知っているような気がする、そんなVさんとの不思議な関係を表現したいと強く思います。
「主に声だけでコミュニケーションをとるような環境において、どう人を理解して好きになっていくか」これが今、最も関心を抱いているテーマです。
実を言うと以前にも「コンテンツ共有サイトにおけるコミュニケーション」から、私の頭の中で思い描くテーマが一度変わったことがあります。「私がVさんに抱いている気持ちはどのようなものなのか」についてです。
一言で表すならば、私は確実にVさんのことが「好き」です。しかしその「好き」は、ごく普通の友人に抱く「好き」とも、恋愛のパートナーに抱く「好き」とも異なるものだと心のどこかで感じていました。友人にしては感情が重いような気もするし、かといって恋愛感情かと聞かれると、決してそうではないと断言できる自信があったのです。
「好き」という言葉の解像度の低さを思い知らされるとともに、私がVさんに抱く「好き」は具体的にどのような感情なのかということに興味を持っていました。
ですが、プロジェクトが進み、研究室のメンバーや先生と意見の交換をするうちに、友人関係が様々存在するように、「好き」という感情にも様々あり、わざわざVさんへの好意を変に特別視して解明する必要もないということに気が付きました。
そもそも、様々に存在する関係を同じ「友人」や「師弟」といった名前で一括りにしてしまうこと自体が、本当は疑問視されるべきことなのかもしれません。
私とVさんの関係は、あくまで「私にとって」の「Vさんと」の関係です。それは私が他に関わりを持っている誰のものとも異なりますし、Vさんにとっても同様でしょう。
だから私はこの関係を、唯一無二であるという意味を込めて、そのまま「Vさん」と名付けました。これは今後プロジェクトが進む中で変化する可能性も否定できませんが、現時点ではこの名前が最も合っていると思います。
最後に、現在も引き続きコーチングを受講しながらプロジェクトを進めていますが、その過程で「記録をとる」といった行為はしていません。なぜなら、あえて記録をとらないことの面白さがあると考えているからです。
初めの頃は、後から個人的に聴き直し、ふり返ることを目的としてコーチングの録音を行っていたのですが、録音をしなかった(厳密には、し忘れた)回の方が、よりVさんの発言をはっきりと覚えていたのです。記憶に残る発言のほとんどが、私に対して言及していたり、私の発言に笑っていたりする場面のものでした。
このように、一種のフィルターがかかった状態で「あの時、私にこう言ってくれていた」と思い出すことが非常に面白いと感じたので、それ以降コーチングの録音を意図的にやめました。
ですが、最終的に発見や学びを表現するためには、何かしらの成果物を作成する必要があります。どのような媒体にするかはまだ決められていませんが、関係「Vさん」を表現するのに最も適切な方法を、「卒プロ2」を進める中で模索していければと考えています。