ガラスの向こうに*1
あたらしい多目的スペース(以下「パビリオン」)や「滞在棟」ができて、キャンパスが変化しつつある。その変化を目の当たりにしているなかで、「みんなでキャンパスをつくろう」という呼びかけは、とても魅惑的だ。夢はふくらむ。だからこそ、「ちゃんとした夢」を見なければならない。そう思うのだ。
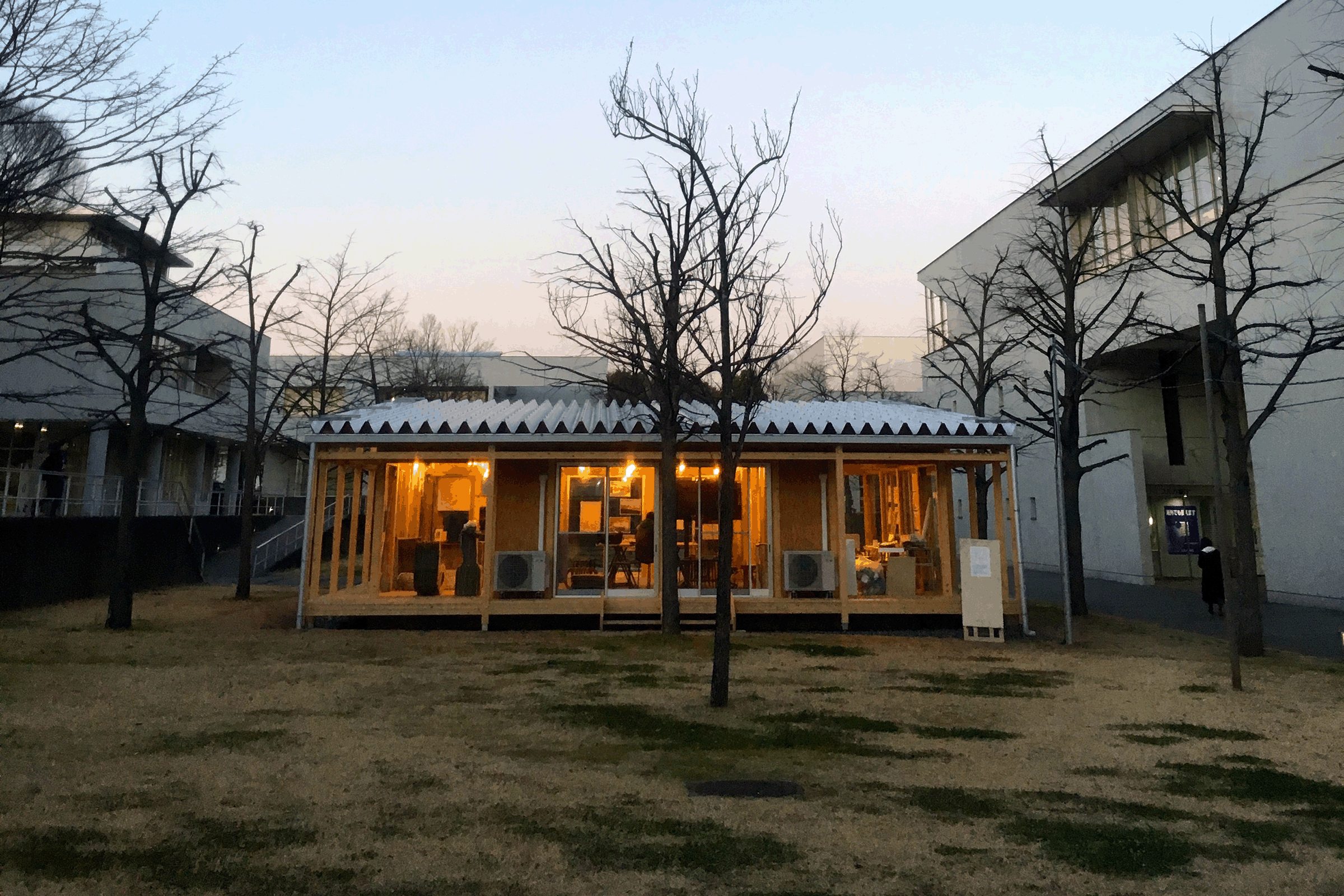
「生活のある大学」を夢見るとき、まずは「共用」ということについて考えておきたい。近年、シェアハウス、シェアスペースといった場所の利用が、ひと頃にくらべて親しみのあるものになってきたが、ぼくたちにとって身近な存在である「教室」も、多くの人と「共用」する場所だ。ふだん、ぼくたちは、あまりいろいろなことを考えずに「教室」を使っている。好き嫌いはあるし、細かい仕様や設備などについて、言いたいことはあるだろう。だが「教室」は、講義や演習のために(それなりの経験やアイデアにもとづいて)設計された空間だ。そして、学生も教員も、「教室」は一時的に過ごす部屋として理解しているので、そのまま受け容れながら使うことが多いはずだ。たまに、設備のあり方について意見を口にする程度だろうか。基本的には、あたえられる環境として、さほど疑うことなく受け容れている。
「パビリオン」や「滞在棟」になると、少し事情が変わってくる。ぼくたちは、もっと主体的に場づくりにかかわろうという姿勢になって、物理的な空間に直接はたらきかけたり、時間のやりくりをしたりする。たとえば、テーブルやイスを並べ替えて、自分たちの活動に合ったレイアウトにする。あるいは、ふだんの「教室」での過ごし方とはちがった時間の流れを実現しようとする。それは、自由であり創意くふうを試される場面でもある。とくに興味ぶかいのは、いつも「教室」でお互いに見せ合っているじぶん(たち)の姿が、とても一面的・限定的であることに気づくという点だ。一緒に空間を整備したり、あるいは泊まったりすると、善くも悪くもぼくたちの人間性がにじみ出るからだ。
「生活のある大学」では、学生も教員も、ふだん以上にじぶんの人格や身体性(つまり、「教員」や「学生」という役割をこえた「生活者」というじぶん)を露呈し合う。あたらしい関係性を発見するためには、じぶんの生活観を、積極的に披露してゆくことが求められるのかもしれない。


あたらしくできた「パビリオン」も「滞在棟」も、できるだけ使ってみることにしている。直接体験は、学びの源泉だからだ。「滞在棟」では一度合宿をしただけだが、「パビリオン」のほうは、「モバイル・メソッド」でたびたび利用している。「モバイル・メソッド」は、ぼくたちの「移動性(モビリティ)」をテーマに、調査研究をすすめるプロジェクトだ。場づくりもコミュニケーションも、ぼくたちが、つねに“移動しているということ(on the move)”を前提にしながら、あらためてとらえなおしてみると、さまざまな発見がある。たとえば、設営や撤収をくり返すための方法や態度について考えたり(We separate to meet again, 2015)、(時にはゲリラ的に)環境にはたらきかけてみたり(Tactical design: Intervention into the cityscape, 2015)、実験にも積極的に取り組んでいる。
今学期、毎回のミーティングは、(参加している3研究室の持ち回りで)「当番」を決めて、場づくりをおこなうことにした。屋外の場合も、「教室」をつかう場合でも、メンバーが90分間をどのように過ごすかを考えながら準備をする。参加者は10名ほどだが、みんな、決められた日の90分間を一緒に過ごす。その前後の時間は、一人ひとりがそれぞれの予定で(ばらばらに)動いている。一日、一週間、一か月と時間の範囲を広げて考えると、90分のミーティングの場は、大いなる時間のなかのちょっとした逗留先に過ぎない。ミーティングは、そもそも仮設的なのだ。だからこそ、その90分をどのように設計するのか、きちんと考えなければならない。お互いに時間を供出し、調整した結果として生まれる場は尊ぶべきものだ。それはまさに「モバイル・メソッド」という方法と態度が発揮される領分だ。


ミーティングの概要は、毎回「ログシート」に記入している。このシートは、写真やスケッチ、経過の説明にくわえて、「空間」「ツール/装置」「活動」という3つの項目で要約するようになっている。それぞれ、どのようにして調達したかという点も書きとどめておきたい。この記録をとおして、道具をふくめた物理的な空間のことだけではなく、さまざまな〈モノ・コト〉の集まりとして、ミーティングという場をとらえておきたいと考えている。まだ数回分しかないが、このシートは、どのような場づくりがおこなわれたのか、そのなかで、どのようなコミュニケーションが発生したのか、後から復原する手がかりになる。
“移動しているということ”に光を当てて、場づくりやコミュニケーションについて考えると、みんなに「共用」される場所は、できるかぎり「無色透明」であるのが望ましいことに気づく。一般的に「多目的スペース」と呼ばれている場所は、文字どおり、使う人のさまざまな目的や用途に応じて、改変できる仕様であることを指している。じぶんたちが使うときには、好きなようにアレンジしたい。それは、(顔を合わせることさえないかもしれない)他の利用者が、同じような欲求を持っていることを尊ぶことによって実現する。ぼくたちは、あくまでも一時的に利用するのであって、時間が来たら、「無色透明」な状態で次の利用者に引き継がなければならないのだ。“移動しているということ”は、設営と撤収をくり返すということだ。
「共用」を支えるのは「原状復帰」の精神である。個人的には、細かいルールをつくるのは好きではないので、多少の時間がかかっても、「原状復帰」の精神を育まなければならないと思っている。「終わったらきれいに片づける」というルールや「規約」をつくって利用者に従わせるのではなく、じぶんたちの自律性を確保するための態度として、「共用」に必要な一連の所作を身につけたい。つまり、次に使う人への気持ちを表明するということだ。「パビリオン」も「滞在棟」も、多くの人に使われることによって、息づいてゆく。まさに「生活のある大学」は、生活をとおして理解される性質のものだ。だからこそ、ゆっくりと時間をかけて向き合わなければならない。まだまだ、これからだ。
ぼく自身は、最近「パビリオン」のガラスに描かれたイラストをちょっと複雑な想いで眺めている。たしかに、カラフルなイラストで空間は華やぐ。きっと、評判も悪くないのだろう。だがそれは、「共用」ならぬ「私用」へと向かう兆しではないのか。「無色透明」は、退屈でも無機質でもない。文字どおり、ガラスの向こうに何があるのかを見とおすことのできる贅沢なのだ。それは「共用」であることの象徴だ。
ひとしきり愉しんだら、「原状復帰」で引き継ぐ。「無色透明」であればこそ、愉しかったであろう場所のようすを想像し、その場に居合わせることのできた人を羨む。それが、コミュニケーションへの欲求になる。
(つづく)
*1:この文章は、2016年6月6日(月)にMediumに掲載したものです。本文はそのまま。→ ガラスの向こうに - the first of a million leaps - Medium