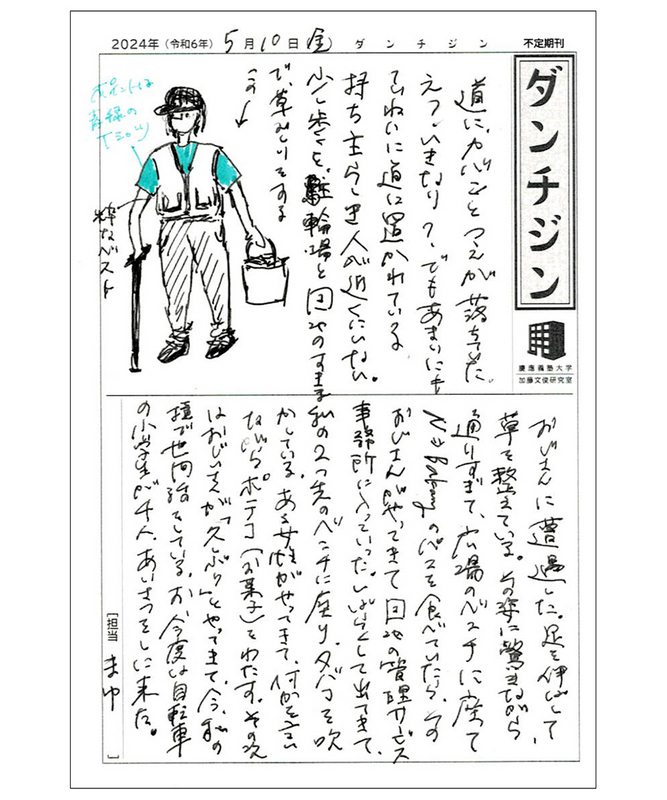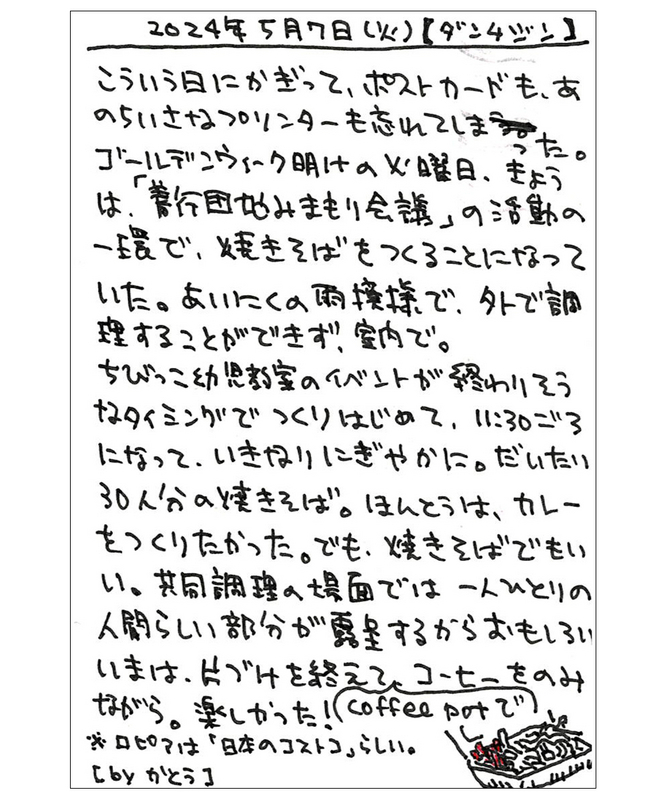(2024年7月16日)この文章は、2024年度春学期「卒プロ1」の成果報告として提出されたものです。体裁を整える目的で一部修正しましたが、本文は提出されたまま掲載しています。
はじめに
新たな場所を訪れた際、その場所に馴染むために、言葉を変えたり、服装を変えたり、ローカルなお店に顔を出したりすることで、あたかもこの場所を知っていたかのようにふるまうことができる。そして、このまちの一員として社会の誰かから認めてもらえているような感覚になれる。もしかするとそれは、まちに溶け込むためのマナーであり、まちで生活をしている他者から課せられたミッションなのかもしれない。このプロジェクトは小学校6年間の間に積み重ねられた日記や手紙、写真や映像、そして人を手がかりに、過去をすくいながら当時は言葉にできなかった思いを、23歳のわたしなりの言葉で文字に表し、過去の自分と現在のわたしを繋ぐプロジェクトである。島をでて10年以上経ったのにも関わらず、奄美大島という場所とそこでの記憶に囚われているわたしがいることを当時は想像もしていなかった。そして当時から、薄々と感じていた島独特の集団意識からの疎外感や、自分自身の島における縦と横の繋がりの希薄さに、孤独さを感じ、どうしようもない劣等感を感じていた。しかし誰かに伝えたところで解決するような問題でもないことは当時も理解していて、もやもやを自分の中の心にしまっていた。シマンチュ(島人)らしく生活をすること。わたしは小学校の6年間の中で、新たな土地で生活をする際は、その「場所らしさ」に馴染む必要性があることに気がつき、適応しながら生活していたようだった。移住して2週間で方言を話し、一人称を「わたし」から「ひなこ」に変えた。スカートやフリルのついた洋服は一切やめて、動きやすい半袖と短パンになった。まだ知らない誰かから評価される「変わり者」を怖がり、奄美大島らしさに馴染むことを知らず知らずのうちに望んでいたのかもしれない。島の人はよく「内地」という言葉を使うが、わたしも小学校4年生の時に参加した、奄美本土復興周年が大々的に行われていることからもわかるように、奄美大島は本土から離れた「離島」という意識が強く根付いており、それほど島内での集団意識が強いのだと感じる。わたしは内地からきたよそ者を隠すことが自分が傷つかない方法だと、15年前から感じていた。それは、奄美大島らしさがよく、人があたたかく、アットホームな雰囲気と語られることの言葉に隠れている、島独特の集団意識やまちでの縦と横の繋がりの強固さを表現しており、2泊3日の旅行者が郷土料理屋や地元の居酒屋を訪れるだけでは、感じえない、つながりへの劣等感逃げる方法である。かつて何度も、集落単位で出身地を問われたり、苗字を聞かれて惨めな気持ちになったように、奄美大島への移住者は生活の要所要所で疎外感を感じざるをえなくなっている。奄美大島に移住した知り合いから「東京にいる奄美の人は楽しい。」という声を聞いたことがあるが、そう感じざるを得ない状況を作っている原因はどこにあるのだろうか。奄美大島で出会った島唄は15年の間でたくさんの出会いと経験を作ってくれた。しかしふと振り返ると、多くの出会いや経験と同時に、それらと相応の苦しさを対人関係やコミュニティにおいて感じる経験もしていた。対人関係やコミュニティへのつながりを強く求められるこの場所で、何を考え、6年間を過ごしたのか、研究を行いたいと考えた。そして卒業後も大切にしていきたい記憶だからこそ、時間をかけて向き合いたいテーマとなった。
日記を通して考える
今回、幼いながらも小さな島の帰属意識に気づきコミュニティに対して、友人に対して、家族に対して何を考えていたのかを思い出す手がかりとして、6年間分の日記や、手紙、文集などの記録を用いた。登場した人物や登場した場所の回数、日記のトピックなどを数値化し、どのような人物と生活をし、どのような発見があり、どのような感情を抱いていたのか、変えることのできない記録から読み取った。日記に登場する人物やトピックには偏りがあり、当時から交流のある友人を再確認すると同時に、学校内では吹奏楽や水泳、学童などのコミュニティに属し、人間関係を築いていたこと、学校外においては6年間続けた島唄教室の話題も多く、当時特に印象に残っていたことだとわかった。また手紙を通して、縦と横のつながりを強くもつことの重要性に駆られていたことに気づいた。兄弟のいないわたしは、学校内でsisという擬似のお姉ちゃんとのつながりをもつことで縦の関係をもとうとしていた。そして信頼され、気に入られることで生活をし易い環境を自分自身で作っていた。さらに学校外においても、わたしという人物を認めらもらうために、あらゆる行事に参加をしたり、他校の小学生とつながりをもつためにキャンプに参加をしたりすることで、あたかも奄美大島が地元であるかのように取り繕い、知ったようなフリをするように努めていた。苗字を聞いただけでどの辺に住んでいるのかが大まかに分かってしまう奄美大島で、友達の友達という関係性の構築がどれほど重要なのか当時から理解していたようだった。しかしそれでも、どんなに頑張っても現在もなお、苦い疎外感から逃れることはできなかった。完璧に取り繕っていても、いつか内地の人間ということがバレてしまった際に、腫れ物のように扱われることは避けられない。わたしはこれからも本当の意味で奄美大島の人間となることはできないのである。わたしには奄美大島がどこへ行っても味方になってくれる故郷と言える資格はないのかもしれない。
それでも、わたしが6年間の生活を乗り越えることができたのは、当時のわたしが活発で目立つことを好んだ性格であったということが記録を通して分かった。学校内外でライバルと競い1番にこだわったり、毎日外に出て家族以上に他者とコミュニケーションを行ったりすることで、自分らしさを相手に伝え、認識してもらい、存在を認めてもらおうとしていた。また他者とつながることや、頼ることに抵抗をもたないことが、奄美大島らしさへの適応もすんなりと果たせたことと関係していると考えた。
そして今回、プロジェクトを通して日記の取り扱いの難しさを学ぶことができた。扱っている日記は、当時毎日の宿題として提出していたものであったため、誰かにみせ、添削が返ってくる文章になっていることから記録媒体として抽出できる部分の少なさが課題として上がった。そのため、今後の扱い方については再度考えていく必要がある。

(卒業プロジェクトにて扱う日記)
友人と会い考える
プロジェクトを始めた当初、わたしはフィールドを広げ、友人にあったり、積極的に奄美大島を訪れることを考えていなかった。しかし6月には日記に名前が多くあがった友人に会い、8月には奄美大島を訪れることを予定している。これは、奄美大島での記憶がわたしだけで作られているのではなく、友人や島という場所との強い関わりがあってこそのものであるということを日記を通して実感したことにある。そして当時のわたしらしさを客観的に評価できる声があることで、より詳細なエピソードや、わたしの忘れていた記憶を思い出すことができると考えたからだ。さらに当時の記憶を共有することで、より思い出が鮮明になり、自分にとっての過去の苦い思いをポジティブなものに捉え直すことができるかもしれないという期待があった。そのような中で6月下旬、6年間の登校をともにした友人と新宿で待ち合わせた。会いに行くまでの気まづさは全くなかった。むしろあの頃のようにふるまえる自信があった。それは友人も同じだったようで、標準語から突然、方言を使い出したり、日常の中に潜むあの時のあの思い出が共有できたり、テンポよく会話が繰り返された3時間に6年間、奄美大島で過ごしたわたしの存在を感じることができた。「島の人と話してたら自然と方言になるから。」と言われたり「島の人とは会えば普通に喋れるかなって思ってる。」と言われることで卒業後別れて10年ほど経っていながらも、彼女の当時の思い出にわたしが存在していたことを感じられた。そして23年間のうちのたった6年間の時間を共有していたのにも関わらず、あの頃のように、お互いがお互いのことを全て知っているような気持ちにさえなった。友人からは、ごく自然に、当たり前に奄美大島の「あの場所」や「あの時間」を共有され、知っていることを前提に話されることが、今も現在も島の一員になれていたような感覚になり、過去の自分が島に馴染むために行っていたふるまいの力強さに驚かされた。そしていつまでも過去の記憶にとらわれ、島での生活を印象深くもっているのはわたしだけなのかもしれないという気持ちも覚えた。わたしが思っているより、奄美大島はわたしという人間を疎外していなかったかもしれないし、内地の人間だという対象として扱っていなかったかもしれない。しかしそれほど敏感に当時は「らしさ」に馴染むことを迫られていた。過去のふるまいを振り返ると、わたしは島の一員になるための奄美「らしさ」に馴染むように無意識に動かされていたようにも感じた。わたし服でスカートを履かないこと、一人称をわたしではなく自分の名前で呼ぶこと、方言を使うこと、このような他者からわたしがその場所にいても良いと認めてもらえるようなふるまいをしなければ、これほど時を超えて友人とのスムーズなコミュニケーションがができていなかったかもしれない。わたしは7歳なりに感じていたルールに倣い、馴染めるようにしていたのだろうと感じさせられた。

(小学校6年間を過ごした学校)
らしさを捉える
過去の記録から始まり、当時の友人と再開する中で島「らしさ」について知りたいと考えるようになった。居心地の良さを感じる一方で、内地の人間がどこか寂しさを感じてしまう奄美「らしさ」はどこにあるのだろうか。これまで「らしさ」を捉える上で、奄美大島全体の風習や風土、慣習などの大きな枠組みと、小学校内でわたしらしさを位置付けるための小さな枠組みがあると考えた。「モビリティーズ 移動の社会学」(ジョン・アーリー)によると、アクセスの概念には、経済的、身体的、組織的、時間的な制約があるという。当時小学生だったわたしがアクセスできたものは、その中でも友人や家族、文化といった組織的なものと学内外の時間的なものであり、だからこそより他者との密なコミュニケーションが求められていたのだと感じた。また本書で弱い紐帯の強さについても語られており、密に織り込まれた小集団が与える強さは大きく、奄美大島で築かれている関係性は、特にこの弱い紐帯の強さに依存している社会だと考えた。そしてわたしは社会的排除から緩和されるために、日常生活を織りなす、交友や家族、インフォーマルなつながりを通して、社交をすることで奄美大島という社会へのアクセスを行っていたのだと考える。実際にご近所付き合いや人とのつながりがなかった島でのわたしの姿を想像することは難しい。人のつながりがなぜ必要だったのかという問いに対しては、このような目に見えないコミュニティや関係性を薄くじわじわと広げていくことで自分の存在を感じてもらうためだと答えることができるのかもしれない。小学校入学時、家族以外に知り合いを知らず、加えてクラスの出身幼稚園が2つだけに別れているという状況の中で自分の居場所をみつけることは簡単ではなかったと思う。それでも6年間休まずに登校をすることができたのは、ご近所付き合いや人とのつながりによって紡がれた、関わりと受け入れてくれたあらゆるコミュニティのおかげであると感じた。
わたしは、場所らしさを比較する際、現在住んでいる神奈川などの関東圏と地元である鹿児島を含む九州、そして奄美大島を想像する。客観的に評価をするならば、大きくはそれぞれ人の流れが異なると感じる。「渋谷学」(石井研二)においては、場所のもつ特殊なシンボル性のなかには取り替え不可能な問題があり、場所性と文化消費に必要な多様なオーディエンスだという。東京のシンボル地とも言える渋谷と比較した際、2つ目の多様なオーディエンスは奄美大島とは大きく異なる。島において、日本人観光客やインバウンドの観光客を増やす働きはあるものの、実際に島に降りたつと方言を話さない人を探す方が難しい状況で、多様さとはかけ離れていることが分かる。そのような環境では、集団意識がより強固なものになることも理解ができるのかもしれない。そしてこのような奄美大島の環境や人、空気、街、あらゆるところから感じられる慣習を身につけることができたわたしは、すでにどの場所でも生きていける力を身につけられているのかもしれないと感じた。
これから
これまで、過去の日記を読み解いたり、友人と会うことを通して、当時のわたしを客観的にみながら、6年間のわたしらしさや奄美大島らしさを徐々に言語化できるようになっている。卒プロのこれからに向けて、より具体的な表現やエピソードを集めるためにも実際に奄美大島を訪れ、参与者として「らしさ」を捉えていきたい。そして引き続き、友人と繰り返し会話を行いながら過去の記憶を紐解いていきたいと考えている。しかし友人とのコミュニケーションを行う中で感じた、お互いの記憶の乖離には慎重になる必要があると感じている。友人と会話を行いながら、一方にとっては大きな出来事と捉えていることでも、他方にとっては記憶にすら残っていない出来事が多くあった。わたしは奄美大島「らしさ」を考える上で、過去の出来事を友人と同じもののように共有し、当時の答え合わせをしていくように紐解いていくことができるのではないかと期待していた。しかし10〜15年前の記憶となると、曖昧になることも多かった。「そうだったような気がする」と相手に合わせてしまう会話では、普段のコミュニケーションと変わらないものになってしまう。そして記憶の改ざんができてしまうと感じている。当時の記憶をそのまま現在にもってくるためにも、繰り返し友人と会うことが必要性を感じており、さらに日記を現場に持ち込むことや、友人の人数を変えることで記憶を広げていくことが必要になると考えている。今後は、引き続き過去の記録を読み解き、当時の自分が何を考えていたのか友人とのコミュニケーションを通して考えるとともに、奄美大島を訪れ、生活を眺めることで風習や風土、慣習などの大きな枠組みの奄美大島らしさを考えていきたい。もう2年ほど奄美大島で半日以上の滞在をしていないわたしが、改めて奄美大島と関わりをもつ。当時の友人のほとんどが島外へ出ている島に長く滞在する理由がなくなってしまっている現在の環境は、15年前、初めて島を訪れた時の環境と似ているのかもしれない。何かと理由をつけて、そこにいても許される理由を探しているわたしにとって、時間が経てば立つほどアクセスがしづらくなっている島に足を運んでみる。少し部外者となってしまった、わたしが今改めて島で生活することでみえる社会はどのようなものだろうか。卒プロのこれからは数年ぶりに奄美大島での生活を眺め、より近くで「らしさ」を感じていきたい。
(岩﨑 日向子|Hinako Iwasaki)