「いつもどおり」で「いつもちがう」
ぼくたちは、全国のまちを巡る「キャンプ」を続けている。ここ数年は、2泊3日で出かけるのが標準的なやり方になった。「キャンプ」では、滞在先で人びとの暮らしにできるだけ接近して話を聞き、その成果をポスターやかわら版などの「ちいさなメディア」にまとめる。初期のころは、ポストカード、ビデオクリップ、音声ガイドなど、フィールドワークの成果をまとめる方法をあれこれと試していたが、いまはポスターづくりの活動として落ち着いている。この一連の活動の原型は、2004年の秋に柴又(東京都葛飾区)でおこなったフィールドワークに遡る。あの頃は、「カメラ付きケータイをもちいた社会調査」として位置づけていた。

【2004年11月9日|日本経済新聞】
柴又のフィールドワークでは、学生たちが(ケータイのカメラで)集めた写真にテキストを添えてポストカードをつくり、まちで配布した。一連の活動をとおして、まちのことを理解するばかりでなく、人びととのコミュニケーションこそが大切だという想いはつねにあった。そもそも、誰かとのかかわりなしにフィールドワークはできないからだ。
柴又のフィールドワークは、日帰りだった。新聞の記事がきっかけで金沢(石川県)に出かけることになり、やがて宿泊をともなう形で全国のまちを巡る活動へと展開していった。しばらくは、「フィールドワーク」ということばで呼んでいたが、基本的な考え方・すすめ方を『キャンプ論』*1として本にまとめる頃から、「キャンプ」ということばを使うようになった。いつも、20名ほどの学生たちとともに出かけるので、「フィールドワーク」という「調査」でありながら、「合宿」としての側面について考えさせられることも少なくない。
この活動をはじめたばかりのころに、実践の事例として「キャンプ」を紹介する機会が何度かあったが、「キャンプ」は「研究なのか教育なのか」を問われることが多かった。また、「地域活性化」や「まちづくり」とのかかわりについての質問もあった。そして、判で押したように、「キャンプ」と呼んでいる活動の「効果」や「影響(インパクト)」をどのように評価するのかという話題になった。「研究なのか教育なのか」という問いには「両方です」とこたえるしかない。そのこたえに不満足そうな人も少なくなかったが、もともと「キャンプ」は「キャンパス」と対比させながら位置づけているので、当然のことながら教室やカリキュラムのあり方について考えているし、まちに暮らす人びとと語らう過程においては、インタビュー調査(広い意味でのインタビュー調査)としての側面が際立つことはまちがいない。
「何のためにやるのか」「どういう意味があるのか」といった問いは、たびたびくり返される。実際には、「キャンプ」という実践を体験しながら学んでいることが、とてもたくさんある。その学びを「続けること」が「何のために」という問いへのこたえなのかもしれない。「どういう意味」かについては、まさに「キャンプ」という場づくりをとおして、コミュニケーションのなかでつくられてゆく性質のものだ。
「キャンプ」は、多くの場合は「一度かぎり」である。47都道府県を巡ろうという発想なので、たいていは「未踏」の対象地を選ぶことになる。そんななか、同じ場所に何度か出かけることもある。たとえば青森県の深浦町では、2015年から3年続けて「キャンプ」を実施することができた。*2

「深浦の人びとのポスター展3」は、本日11:00から。 #fukap3
2017年5月、3度目の「深浦キャンプ」をおこなった。すでに別のところで書いているが、活動を継続していくなかで、ぼくたちが考えるべきなのは「慣れ」の問題である。いま、あらためてふり返ってみると、3度目の「キャンプ」を実施するにあたって、さまざまな手続きが、とても上手くいった。それは、3年をかけて、ぼくたちが、深浦での「キャンプ」のやり方を体得してきた証だ。学生メンバーは学期や年度ごとに出入りがあるが、全体の企画やファシリテーションにかかわるメンバーどうしで、「いちいち言わなくてもわかること」が、たくさん共有されるようになったのだろう。
初めて深浦に行くことになったとき(2015年6月)は、事前に都内で打ち合わせをしたり、下見に出かけたりして準備をすすめた。2年目は都内でのミーティング、3年目はメールでのやりとりだけで「本番」に臨んだ。もちろん、日程のやりくりの問題もあったと思うが、ぼくたちは、過去の2回をとおして、準備や運営の「しかた」を一緒に学んだのだ。それは、すべてが言語化・形式化されているわけではなく、少しずつ積み重ねられたコミュニケーションとともに、身についたものだ。
そのおかげもあって、3度目の「キャンプ」は、ほぼ予定どおりに、淀みなく進行した。取材からポスターづくり、印刷、成果発表会にいたるまでの一連の流れは、とてもスムースだった。そのいっぽうで、「言わなくてもわかること」だと想定して、コミュニケーションが疎かになっていたのかもしれない。もちろん「馴れ合い」だったなどとは、全く思わない。
ごくあたりまえのことだが、ぼく(そして準備や運営にかかわるメンバー)にとって3度目であったとしても、今回が初めての「キャンプ」だという学生が何人もいた。そのことへの配慮は、じゅうぶんだっただろうか。「キャンプ」は、「まずは、やってみなければわからない」という経験学習の考え方に依拠しているからなおさらのこと、いささか説明不足であっても、身体で覚えればいいと考えがちだ。
すすめ方や活動内容は「いつもどおり」だったとしても、つねに「いつもちがう」のだ。このことをきちんと自覚していないと、「キャンプ」は、少しずつ綻びを見せはじめる。ポスターも成果報告会も、見かけ上は、さほど変わらないように映るかもしれない。だが、ちょっとした連絡不行き届きや調整の甘さが、全体としての質を確実に左右する。
「まち」はどこにあるのか
「キャンプ」は、慌ただしいプログラムだ。すでに述べたとおり、(まだ漠然としてはいたものの)柴又に出かけたころから、調査の成果を、対象となった人びとに還すということを意識していた。協力をお願いしたのだから、素朴にお礼をしたいという想いもある。くわえて、論文や報告書という形だけが「成果」なのではなく、もっと身近なやり方を探すことが大事だと考えていた。
できるかぎり出先で(つまり滞在中に)成果をまとめて、その場で発表したり、成果物を渡したりすることにも取り組みはじめた。ぼくたちは、「成果がまとまったら、あとでお送りします」などと言って現場を離れることが多いのだが、実際にはフィールドワークから帰ってくると、つい後回しになってしまう。もちろん、それはぼくたちの問題ではあるのだが、旅が終わると達成感もあって気が緩んでしまう。だから、「宿題」を持ち帰らないようにするのがいい。滞在中に、成果をまとめてしまえば、きっとスッキリするにちがいない。そう思って、「キャンプ」では、最終日に成果報告会を組み込むようになった。「宿題」をかかえたままでいることなく、出先のことは出先でひと区切りつけてから、清々しく帰るためだ。
典型的には、「キャンプ」の最終日に開く成果報告会に取材対象となったかたがたを招いて、その場で完成したポスターを披露する。もしかすると訪れることもなかったまちで、会うはずのなかった人と、「キャンプ」という活動をとおして語らう。そして、わずか数時間のやりとりのなかで、その人の「生き様」に触れる。「インタビュー」や「取材」ということばを使って協力をお願いするが、実際には世間話をするようなものだ。取材をお願いしたみなさんからは、「ただおしゃべりしただけだった(あれでよかったのだろうか)」「じぶんばっかり話していた(あまり取材された感じがしなかった)」などといったコメントが返ってくることもある。でも、それでいい。というより、それがいい。ざっくばらんな話のなかにこそ、その人の「らしさ」がにじみ出ると考えているからだ。
もちろん、世間話であったとしても、その時間をふり返りながら、ひと晩でポスターにまとめるのはそう簡単なことではない。会ったばかりの人のことを想いながら、夜更かしして、ポスターを仕上げる。そして成果報告会では、取材のようすや、ポスターをつくるにあたってどのようなことを考えていたのか、順番に発表してゆく。それぞれのポスターには、学生たちが感じたこと・考えたことが埋め込まれている。成果報告会は、笑いも涙もあって、いつも感動的だ。このひとときのために「キャンプ」があると言ってもかまわないくらいだ。それは、ポスターをつくるために時間やエネルギーを投じたことが、報われる瞬間でもある。
成果報告会が終わるとドタバタと片づけて帰路につくので、その後のポスターの行方については、じつはきちんと把握できていないことのほうが多い。たとえば「深浦キャンプ3」では、役場のロビーにポスターを展示し、その前で報告会を開いたが、そのまま深浦をあとにした。つくったポスターは、「おきみやげ」として、その場に残したままでぼくたちは「キャンプ」を終えた。
あとから、「キャンプ」をとおして出会った人から、ハガキやメールが届くことがある。ぼくを「迂回」して、直接、取材に赴いた学生たちに届くことも少なくない。残念ながら、近親者から訃報が届くこともある。ポスターそのものが、遺影に使われたという話を、たびたび聞いた。もちろん、悔やむ気持ちでいっぱいだ。あんなに元気そうだったのに、と驚かされる。同時に、学生たちが、故人の笑顔や自然なふるまいを、上手くとらえたことの表れなのではないかと感じる。ポスターも、そしてポスターのなかの人物も、少しずつ歳を重ねる。
「深浦キャンプ」のように、同じ場所にふたたび赴く機会があると、ぼくたちがつくったポスターと再会することもある。2回目となる「深浦キャンプ2」(2016)のときのポスターを、それぞれの場所で見ることができた。「厳しいよ ここは」という、1年前のコピーは、いまはどのように響くのだろうか。「クセになる、曲者」の日常はどのように流れているのだろうか。成果報告会を経て、一枚一枚のポスターが、どこで、どうなってゆくのか。これについては、少し時間をかけて、ゆっくりと見守るしかないだろう。

【2017年|「深浦キャンプ2」(2016)でつくったポスター】
2017年6月に実施した「那珂湊キャンプ」は、あらためて「まちに還す」ということの意味をふり返るきっかけになった。このときは、那珂湊駅(ひたちなか海浜鉄道湊線)のホームを借りて、成果報告会を開いた。そして、取材先のかたがたの多くが、足をはこんでくれた。こぢんまりとした集まりだったので、その分、感情に充ちていたように思う。ふだんは、成果報告をしつつ、役場のロビーやギャラリーなどに貼ったまま帰るのだが、今回は、可能なかぎり、その場でポスターを手渡すことにした。
ポスターをつくった学生(ペア)から、直接、本人に手渡す。つまり、「まちに還す」のではなく、「人に還す」場面が生まれた。さらに厳密に言えば、「人」のところには、具体的な「名前」が入るので、たとえば 「尾澤さん」に、「川崎さん」に、あるいは「奥山さん」に、それぞれ還すということだ。ぼくたちは、知らず知らずのあいだに、「まち」という顔の見えない存在を相手に活動するようになっていたのではないだろうか。そもそも、感謝の気持ちを込めて、成果を一人ひとりに還そうとしていたはずだ。
2017年度前半に実施した「キャンプ」は、対照的だった。「深浦キャンプ3」は、3年目(3回目)となって、惰性や弛みを心配するほどにお膳立てされていた。「那珂湊キャンプ」は、学生たちが中心となって準備をすすめたので、やや粗削りな構成だった。*3「まち」という、ひとつのまとまりが際立つ「キャンプ」。そして、特定の名前とともに「人」の顔が際立つ「キャンプ」。いずれも、ぼくたちの「キャンプ」である。こうしたバリエーションに気づくことができるのも、「いつもどおり」で「いつもちがう」からだろう。🐸(つづく)

🐙「那珂湊の人びとのポスター展」は、こんな感じです。 #nakap
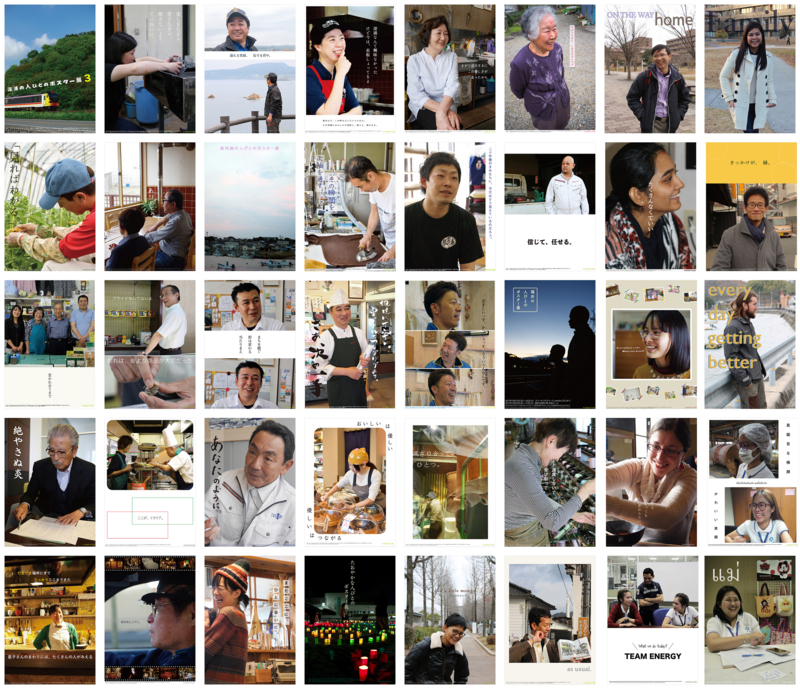
【2017年度のポスター|深浦3・那珂湊・福井・東広島・バンコク】
*1:加藤文俊(2009)『キャンプ論:あたらしいフィールドワーク』慶應義塾大学出版会
*2:深浦のほかにも、金沢、坂出、富山、小諸、氷見、釜石には2回以上訪れている。
*3:「那珂湊キャンプ」は、「慶應SKC計画(https://www.facebook.com/groups/skckeio/)」のプログラムでである。「慶應SKC計画」は、慶應義塾創立150年記念の未来先導基金の公募プログラムとして採択されたもので、2017年度は学生主導の13のプログラムが実施された。